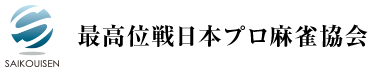──ほう、相変らず鋭いな!
たった今、スーさんがツモったアガリを見て私はいつもながら、感心してしまった。











 ドラ
ドラ ヌキ
ヌキ





この手牌でリーチをかけ をツモったのだが、これ自体はどうということはない。
をツモったのだが、これ自体はどうということはない。
問題はスーさんがリーチをかけたときの打牌で、それが だということなのだ。
だということなのだ。
スーさんのそれまでの捨牌を見ると、明らかに を打つ前は、
を打つ前は、












 ドラ
ドラ
このダマテンだったはずで、 を引いて
を引いて 打ちでリーチにきたのだ。
打ちでリーチにきたのだ。
先の手牌でダマテンするのは初歩の初歩であるが、黙って伏せた私の手牌が、












 ヌキ
ヌキ

こうだったことが、スーさんの鋭さを感じさせたのだ。
「金子君とトド松、ケン坊にドンさんの4人で場が立ったんだって?」
今のアガリの分を受け取りながら、突然スーさんが話しかけてきた。
「えぇ、あんまり動かなかったですけどね」
「でも、トド松が負けたんだろ。4人打ちじゃ、サンマーのようにはいかないか」
「負けたっていっても二十でしょう、負けたうちになんかはいりませんよ。さすがにシブといですよ」
「ほう、言うことがちがうね。でも木村って言ったっけ、あの旦那の1人負けっていうのが面白いね」
「傑作なんですよ。打ち手が負けてないのに、外ウマの1人負けなんてことがあるんですね。帰るときドンさん、サイフに入り切らないぐらい勝ってましたからね。百はいったんじゃないですか」
「当然、共同戦線を張ったんだろ。それで、その3人相手に勝つんだからあの男だけは別格だな」
「そりゃそうですよ。よっぽど自信がなきゃああも平然とした顔をしてられるわけがないですからね」
といった具合にドンさんの強さが話題になっていた。
驚いたことに、私とトド松、ケン坊の3人がドンさんに挑んだということが、すでに私のシマ内では話題になっていて、今日も「J」に入るなり、
「よう金子ちゃん、一昨日凄いメンバーで一戦やったんだって」
いきなりマスターにこう言われ、
「へぇ、よく知ってますね」
「みんな知ってるよ。でも、よくそんなメンバーでやる気になるよ。全然オイシクないじゃないの。オレだったらすぐに逃げるがね」
確かにその通りで、勝ち負けだけを重視するんなら、そんなメンバーでやらないほうがいいに決まってる。
『麻雀必勝法というのがあるとしたら、自分より弱い相手を選んでやることだ』
と誰かが言っていたけれど、冗談じゃない、そんなことをするぐらいなら麻雀なんかやるもんか。負けるのは確かに嫌だが、それ以上にシビれるような麻雀を打ちたい。
私だけじゃない。麻雀職人達は間違いなくそう思っているはずで、そうじゃなきゃ、一定レベル以上に強くなんかなりっこない。
それも、強くなればなるほど強い相手と打ってみたくなるもので、人間っていうのは自分の力を試してみたい、そんな気持が必ずあるものだ。
ドンさんがいくら強かろうが、勝負を挑まれて逃げるわけにはいかない。というよりも、機会があればいつでも挑戦したいぐらいだ。
「別にこっちはいつだって受けますよ。ドンさんだろうと、トド松だろうと、逃げやしませんよ」
こんなふうにツッパってみせたのには、元銀行員らしい堅実な考え方のマスターに対する反発も少しは含まれていた。
マスターはそれに答える代りに、私に向かって意味不明な笑みを返しただけだった。
局面は相変らずスーさんがリードしていた。
私の方はまだ調子が出ない感じで、マイナスはしているが、一吹きで取り返せる程度のものでしかない。
マスターが大敗になっていた。いや正確には勢いが大差というだけで、金額的にはそこまでいっていない。
こんな局面があった。
マスターが10巡目に、「リーチ」といって牌を横に曲げた。その仕草に、今度こそはアガれるだろうという気配がありありと感じられた。
実際、この20局余り、マスターには一度のアガリもなかった。このへんがサンマーの恐いところで、落ち目はとことん叩かれるのであって、純粋なアガリ競争をすれば、どんなにうまく打とうがやはり紙一重の差でやられる。
この局も、マスターのリーチに対して、スーさんが向かう。リーチの雰囲気からして多面張なのは間違いないだろうが、スーさんはそんなこと気にかけるふうもなく、


 と脂っこいところをビシビシ勝負していった。
と脂っこいところをビシビシ勝負していった。
ここが肝心なところで、ツイているときにリーチやダマテンに対して絶対に手牌を曲げてはいけない。
例えば、






このマチでテンパイしているところへリーチがかかった。
そこへ引いたのが 。
。 は現物だが
は現物だが
 は通っていない。
は通っていない。
さてどうする。
これは切りなさい。ツイていればの話だが躊躇なく切りなさい。当たったっていい。もしそれで放銃っても後悔してはいけない。ただし で当たったら、しなければならないことがふたつある。
で当たったら、しなければならないことがふたつある。
 で放銃したことを認識すること、当たったからツキが落ちるのではなく、思っていたほどツイてなかった認識の甘さを改めること、たったこれだけのことである。
で放銃したことを認識すること、当たったからツキが落ちるのではなく、思っていたほどツイてなかった認識の甘さを改めること、たったこれだけのことである。
放銃つこと自体はさほど問題ではない。
 を打たずアガリを逃がすほうがツキを落とす原因なのだ。
を打たずアガリを逃がすほうがツキを落とす原因なのだ。
これは一局の問題ではなく、その後何十局に響くものだから重要なのである。
だからマスターのリーチに対して、スーさんが一歩も退かないのは当然であって、これは後々のことまでを考えているのだ。放銃っても、おそらく今の状態なら一局だけの現象として処理できる。
だが、放銃たないようにしたために、万が一アガリを逃がすことになっては、何十倍かわからぬほどの損になってしまうのはみえているのである。
いくら多面張がわかっているとはいってもそのことになんら変りがあるわけがない。
4巡、5巡、まだマスターはツモれない。
多面張なのだろうが、落ち込んでいるマスターでは、なんとなくアガられるような気がしない。案の定、とうとうスーさんが、こんな手をツモアガってしまった。








 (ポン)
(ポン)

 ヌキ
ヌキ


「う~ん、マイッタ!」
と言ったのはマスター。
「この手をみてくれよ」
手牌を公開することなど滅多にないのだがさすがに呆れたといった感じで倒してみせた手牌は、











 ドラ
ドラ ヌキ
ヌキ





「あ~、これはヒドイね」
半分本気で、半分これが麻雀さ、と思いながら私は言った。
「う~ん、こんな日に限って誰も来ないんだよな」
さすがにマスターも観念したらしく、珍しく泣きを入れた。
麻雀は状態が決まるまでが勝負で、1人がこういう状態になってしまえば、後は取り放題である。
私もマークするのはスーさんではなく、マスターの方で、このままコロしておけば、こちらの身は安全なのである。
そこへひょっこりトド松が現われた。
「いやー、助かったよ。もうフラフラにされちゃったよ」
天の助けとばかりに席を立つマスター、確かにこれ以上ないグッドタイミングである。
「ずい分遅い出勤だね、やっぱりおとといの一戦が堪えたのかな。歳だねぇ」
と私。
「バカ言え、ネコちゃんみたいにノンビリしてらんないよ。オレはきのうも来ているよ」
「えっ、きのうも来たの!」
これには驚いた。丸二昼夜近い激闘が終わったのが昼近く、それで夜出てきたというのだから驚くべきタフネスさである。
「あんただけだよ来なかったのは。ケン坊だって、ちゃんと来ていたぜ」
「えっ~、ケン坊も!」
まったく、この2人にはかなわない。こっちも麻雀には命を賭けているつもりだが、この2人だけは麻雀をやるために生まれてきた男達だとつくづく思う。
「それにしてもドンさんて強いねぇ。あんなのとじっくりサンマーを打ったら面白いだろうね」
とトド松。
サンマーの王者と自他共に認めるトド松が「ドンさんとサンマーを」と言うだけでもドンさんの強さがわかるが、このセリフは、4人の中で自分だけが負けた照れ隠しの意味もあるようにも思えるし、サンマーに対する自信とも受けとれる。
と、その時、
「おや、珍しいね、どういう風の吹き回しですか」
というマスターの声に振り向くと、入ってきていたのはドンさんだった。
「なんでもやるとは聞いてましたけどね、サンマーも得意種目ですか」
と私。
「いや、サンマーはカモだよ。ただ近くまで来たもんだから、ちょっと覗いてみようかなと思ってね」
これは社交辞令のようなもので、サンマーがカモなんてことはありっこない。
本当についでに寄っただけなのか、今度はサンマーでじっくり戦ってみようとわざわざ出向いてきたのか、それはわからぬが、そんなことはどっちでもいい。
落ち目のマスターが抜け、トド松とドンさんが入ってくるだけのことで、これまでの経過は捨て、また一から仕切り直しになるだけのことだ。
スーさんも同じことを考えたのだろう、
「じゃ私が抜けましょう。たまには一杯飲んできますよ」
好調だったスーさんだが、仕切り直しとなればまた最初のツキの取りっこということになり、結果はどう転ぶかわからない。ここはまあ、固く一勝しておきましょうかということで誰にも異存はない。
だいたい、サンマーは3人ちょうどでやるものなのだ。
4人でやる場合は、放銃かツモった場合に和了者の下家が抜け番になってしまうので、本来のツキの取りっこという意味からするとちょっと違った競技になってしまう。
だからスーさんが席を立ったことはむしろ歓迎できた。
トド松とドンさん、それに私の3人が戦うことになったが、キツイメンバーになったものだ。
ただ私は、この組み合わせを内心望んでいて、このメンバーならシビレるような麻雀が打てる。むしろ望むところなのだ。
ところが、席に着くなりドンさん、
「サンマーじゃ金子君とサシウマはいけないな。どうだ1本でやろうじゃないか」
(いっぽん!)
さすがにちょっと動揺した。
トド松はイヤというはずがないとみて、私に誘いをかけてきたのだろうが、1本といえば通常の5倍、1時間もツケば1年間暮らせるぐらいのものが動いてしまうのだ。
サンマーというのは、何度も言うようにツキの取りっこであって、途中経過で動く金額などは、紙切れと同じと思わなければならない。レートがいくらであろうと、それは同じことだ。
──はたして、1本でそれができるだろうか。
動く金額で動揺したら即座に負けである。
ちょっと迷っていた。
単に自信の表われか、それともこれがドンさんの作戦か………。
そのときだった。
「金子ちゃん、やんなよ」
と声をかけてきたのはマスター。
分厚い封筒を取り出して、私の横にドサッと置いた。ノリという意味である。
「さっきの一言、気にいったよ」
「なんだよ、さっきの一言って」と、トド松。
「まあ、いいですよ。やりましょう」
元銀行員らしい──などと思っていたマスターがのってきたことが、私を無条件にヤル気にさせていたのだ。
“