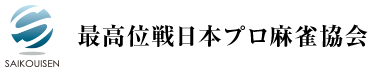聞き慣れた声が電話口に出た。
「アラ、金子様、さきほどお電話をお入れしましたのに」
その声を無視するように
「ケン坊、いってる?」と答えると、まるで子供がムキになってるみたいですねといわんばかりに、クス、と笑うような感じで、
「ハイハイ、さきほどからおみえになっておりますよ。金子様はどのくらいで」
「-40分ぐらいかな」
ときわ台から池袋まで東上戦で12分、そこから地下鉄に30分も乗ると銀座の駅に着く。
駅から降りて、京橋との境にある頭のトンガった交番の手前を右に曲がると、目的の雀荘がある。
さほど豪華ではないが、銀座らしいちょっと高級そうな店の中に入っていくと、見なれた常連達の間では、もう打牌の音も高くなっていたが、ヤツはラスの後らしく観戦の方へ回っていた。
「昨日はどうもな」
もちろん、昨日はうまくやられたな、という意味なのだが、
「イャー、たまたまだよ」
そんなことあるさと、素気ない。
「木村様と上原様が20分くらいでおみえになるそうです」
電話の女性がお茶を運んでくるのを、また無視するように、
「じゃ、美味いコーヒーでも飲んでくるわ」
と、ケン坊の方を向いてしまった。
あらあら、今日はご気嫌がよろしくないようですね、そんな感じでまたクスリと笑う。
恥ずかしくなるくらいその通りだった。
隣りにちょっと美味いコーヒーを飲ませてくれるところがある。そこへ入ると、
「昔のお前はヘボだったがな」
強くなったな、という意味と、まだまだお前には負けんよ、そんな感じで口を開いた。
「そりゃあ、昔は皆んな弱いに決まってますよ」
年下のせいもあって、昨日の大勝など忘れたように素直である。
次に、(それにしても、あの 打ちは見事だったな)と言いかけたが話題を変えた。
打ちは見事だったな)と言いかけたが話題を変えた。
高田馬場時代だったら、打ち終わった後なんかは喫茶店なんかでその話に夢中になったものだ。
時の経つのも忘れて。
それに比べて今は、その頃のように手放しで夢中にはなれない。
お互いに自分の考えを夢中になって言い合えるほど純粋じゃないのかもしれないな。
よくいえば大人になったのかもしれないが。
あの頃の高田馬場の喫茶店に時間が戻ったならきっとこんなふうに話がはずんだに違いない。








こんな捨牌があったとする。
「これは となにかのシャンポンだよな」
となにかのシャンポンだよな」
「当たり前だ。そうじゃなかったら、なんで、 の後に安全牌の
の後に安全牌の がツモ切られて
がツモ切られて が残されているんだ」
が残されているんだ」
つまりこうだ。 打ちの後に安全牌がツモ切られているということは、
打ちの後に安全牌がツモ切られているということは、
 という単純形のカン
という単純形のカン を嫌ったわけではなく、
を嫌ったわけではなく、![]() がなんらかの形で手牌に関係があったからである。
がなんらかの形で手牌に関係があったからである。
しかも よりも
よりも という外スジに気があったということは、もちろん端メンツに関連している。
という外スジに気があったということは、もちろん端メンツに関連している。
その場合、

 も
も
 もない以上
もない以上

 と
と

 に絞られてくるが、
に絞られてくるが、


 の形なら内に寄せて手作りするのが普通であり、ここでも端に気があったのがわかる。
の形なら内に寄せて手作りするのが普通であり、ここでも端に気があったのがわかる。
「しかし三色があれば、 を残すな」
を残すな」
「バカだな、この捨牌が三色に見えるか」
手役がなければ、


 からの
からの 切りは、対子(役牌)+
切りは、対子(役牌)+

 の形に決定され、
の形に決定され、
それならば よりも
よりも の方が安全度が高いというわけだろうが、それならば手役がない以上、
の方が安全度が高いというわけだろうが、それならば手役がない以上、
 を切ってペン
を切ってペン に受けるには特別な事情がなければならない。(念のため、
に受けるには特別な事情がなければならない。(念のため、 が単なる雀頭ということはない)
が単なる雀頭ということはない)
たとえば、ペン が出やすくなっているとか、
が出やすくなっているとか、 が2枚切れているとかといった。
が2枚切れているとかといった。
そういったものがない以上、
 手出しといった先の捨牌は
手出しといった先の捨牌は

 を本線と見るのが正しく、
を本線と見るのが正しく、
また、このケースは実線では驚くほど多く出てくる。
1と9はメンツに使いづらく、出てきやすいという固定概念と、自分が読めないものだから相手も読めないと思っているから、捨牌を工夫しようなんて気にはならないらしい。









「じゃ、こんな下の三色が臭う捨牌だったら とのシャンポンよりもペン
とのシャンポンよりもペン の方がクサイか」
の方がクサイか」
「それにしたって、 手出しの事実を忘れちゃいけない、字牌と
手出しの事実を忘れちゃいけない、字牌と のヒッカケの
のヒッカケの は出やすいと思ってる連中は多いからな」
は出やすいと思ってる連中は多いからな」








「こんな捨牌も とのシャンポンが臭うな」
とのシャンポンが臭うな」
「確かにそうだ、

 なんていう形は
なんていう形は
 が切れ過ぎているか、なにかをポンした時の雀頭候補、手役がらみ、以外の時は中盤過ぎまで引張られることは少ないからな、これもやっぱり
が切れ過ぎているか、なにかをポンした時の雀頭候補、手役がらみ、以外の時は中盤過ぎまで引張られることは少ないからな、これもやっぱり

 +対子で、しょうがなくリーチまで引張られるケースが多いな。
+対子で、しょうがなくリーチまで引張られるケースが多いな。
まったく、捨牌なんかおかまいなしに1と9なら出ると思っているヤツが多くて困るよ」
「まあ、普通だったら、2、3でリーチは1、7、8でリーチは9が危ないと思っておけば間違いはないな」
「あの

 というのは、そういった基本的な形を煮つめていき、余けいなものを全て省いたようなものか」
というのは、そういった基本的な形を煮つめていき、余けいなものを全て省いたようなものか」
「つまり、応用問題だな。それを即座に解くなんざ、さすがだな」
しかし、それに対しては、ケン坊はたぶんこう答えてくるだろう。
「そんな基本形をいくら説明しても、わかんないやつはわかんないよ。わかるやつは

 といっただけでわかるもんだ。
といっただけでわかるもんだ。
その場ではわかったような顔をして聞いていても、内心じゃ、入り目かもしれない、なんて思って聞いているんだ。
そんなやつはいつまでたっても読めるようになるもんか」
そうして、一息おいて、
「だいいちオレだって、 を打つときそんなこといちいち考えるもんか。
を打つときそんなこといちいち考えるもんか。

 、たったそれだけのところから、全ての牌が
、たったそれだけのところから、全ての牌が に集中されるぐらい、鋭利な感覚の持ち主、つまりそれだけ才能を持ったやつじゃなければわからない。そして、その才能も毎日のように磨かなければ切れ味が鈍るもんだ。口で言ったってわかるもんじゃない」
に集中されるぐらい、鋭利な感覚の持ち主、つまりそれだけ才能を持ったやつじゃなければわからない。そして、その才能も毎日のように磨かなければ切れ味が鈍るもんだ。口で言ったってわかるもんじゃない」
そんな話が高田馬場の喫茶店で始発の動くのも忘れて続けられるだろう-。
そして私はいつも思う。
形勢判断、形の良し悪し、読み、そして最も大切な大局観、それらの土台になるのはセンスだ。そのセンスを磨く努力を怠るようなら麻雀をやめよう、と。
2
「金子さん、どうしたの深刻な顔をして」
どうせ麻雀のことしか考えてないのがわかっているくせに、からかうように聞いてくる。
「そろそろ、先生達がくる頃だろ」
先生というのは、電話の女性が言っていた2人のうちの木村の方である。
この人は本業は医者なのだが、それで先生と呼ばれているわけではない。
この人に変わったクセがあって、自分の読みをいちいち口に出して披露するのである。
その読みというのが傑作で、たとえば、








こんな捨牌だと、判で押したように、
「間四ケンか、
 が本線だな」
が本線だな」
思わず吹き出してしまいそうになるが、本人はそう信じ込んでいるのだ。
間四ケンというのは確かに危険スジであるが、 と
と がどういう具合に切られるかによってまるで違うのである。
がどういう具合に切られるかによってまるで違うのである。
つまり、両方ともツモ切りの場合は、まるっきり手牌に関係がないからツモ切られたのかもしれないし、たまたま
 ともっていて切られたのかもしれない。
ともっていて切られたのかもしれない。


 の形からまず
の形からまず が打ち出され、それから
が打ち出され、それから を引いて
を引いて が打ち出される、そういった場合でも、その前後の手出し牌、ツモ切り牌との関連によって、本当に
が打ち出される、そういった場合でも、その前後の手出し牌、ツモ切り牌との関連によって、本当に
 からなのか、違った形からの
からなのか、違った形からの 手出しなのか推理することができる。
手出しなのか推理することができる。
たとえば簡単な例が、 手出しの前に、
手出しの前に、 がツモ切りされていれば、当たり前のことだが
がツモ切りされていれば、当たり前のことだが
 からの
からの 手出しではない。
手出しではない。
先生の読みというのは、そういったことを一切無視して、ただ と
と が切れていれば間四ケンだから
が切れていれば間四ケンだから
 が危ないという読みなのである。
が危ないという読みなのである。
そうして、こう言うのである。
リーチのマチがたまたま
 だった時は、手の内から
だった時は、手の内から を見せながら、
を見せながら、
「やっぱり、これ一点なんだよな」
それに対して皆の反応は、
「やっぱり先生の読みは鋭いや」
と口を揃える。
自信を失なわせてはいけないのである。
先生、というのは読みの先生ということ。
この日も初端にそんな局面があった。
南1局、南家のトド松という男がリーチ








すかさず「
 の一点だな」と、先生の読みが入る。
の一点だな」と、先生の読みが入る。
私の手牌はというと、








 (ポン)
(ポン)


ここまでややリードしていたが、オリる気はなかった。東がドラなのである。
 でアガればインパチ、ツモればオヤバイ。とことん勝負!さあ、ツモれ、と力を入れてツモると、ナント!これだけは打てない牌をを引いてきてしまった。
でアガればインパチ、ツモればオヤバイ。とことん勝負!さあ、ツモれ、と力を入れてツモると、ナント!これだけは打てない牌をを引いてきてしまった。
 かって?そんなもん一発でツモ切るに決まってる。そんなんじゃない。
かって?そんなもん一発でツモ切るに決まってる。そんなんじゃない。
あの捨牌にはどうしても打っちゃいけない牌がひとつだけあるのだ。
さて、それは何か。また、どうして打てないのか。
ヒントをひとつ。先生がオレの捨てた ポンで、
ポンで、






こんな捨牌をしている。
“