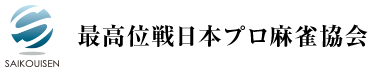最高位戦北海道C2リーグの松本亮一です。
40期後期リーグ戦が始まりました!
新しいメンバーも増え、今回からC1とC2がそれぞれ分かれて戦う本来の
形式で運営できるようになりました。
ですがAリーグまで作るには現在の倍の人数が必要であり、まだまだ北海道
リーグを大きくする必要がありますので全員で盛り上げていきたいと思います。
そんな訳で、今回も自戦記を書かせて頂きますのでよろしくお願いします。
******************************************************
1回戦
木村(元)、田淵、柏井、松本の並びでスタート。
東1局、親の木村から先制リーチが入り、いきなり後手を踏む。
しかし形は崩さず、まわしながら打つこと17巡目、柏井の鳴きにより下記にて
1300/2600+リーチ棒の6200点をゲット。












 ツモ
ツモ ※ドラなし
※ドラなし
その後、流局が続いて親番を迎える。
東4局4本場
柏井から先制リーチが入るが私は全く勝負にならない手牌で
あったため、全力でオリに。
しかしハイテイがまってきたところで、完全な手詰まり状態。
苦し紛れに のワンチャンスで打った
のワンチャンスで打った がつかまり8000は9200の放銃となる。
がつかまり8000は9200の放銃となる。
そんな後ろ向きな放銃をしたのにも関わらず、続く南1局で以下の配牌を手にする。













しかし、ここから聴牌を入れるまでに7巡もかかることに。
やっと有効牌となる をツモる。
をツモる。
 は既に場に2枚切れており自分で4枚使いの
は既に場に2枚切れており自分で4枚使いの
 、非常に自信がなかったが
、非常に自信がなかったが
前局の失点を取り返したいため、即リーを選択。
数巡後、親の木村から追いかけリーチが入る。
嫌な予感しかしない・・・
一発目で持ってきたのが 、私の待ちである上スジにあたる牌である。
、私の待ちである上スジにあたる牌である。
案の定、この が親リーに一発で刺さり、9600の失点となった。
が親リーに一発で刺さり、9600の失点となった。
その後、1300/2600などの加点をしたが、トップまでは届かず1回戦目は
2着の+10.3pとなった。
2回戦目は抜け番のため省略。
3回戦
柏井、田淵、松本、岩崎の並びでスタート。
東1局 ドラ













これを6巡目に聴牌したが、ドラ引き、または 引きのタンヤオ変化を見てダマを選択。
引きのタンヤオ変化を見てダマを選択。
すると次巡あっさり をツモり400/700をものにする。
をツモり400/700をものにする。
東場は小場で周り、南3局での親番で田淵から親満を出アガり、トップ目で迎えたオーラス。
2着目の柏井との差は5900。
自分でアガって終わらせたいが、それは無理な配牌であった。
最悪流局を希望したが、親の岩崎のリーチ宣言牌の中が柏井のチートイドラドラにつかまり
見事に逆転される。
2回戦目も2着で、+20.9pとなった。
4回戦
松本、田淵、岩崎、木村の並びスタート。
席決めで、1~3回戦全てラスの席に座ることになった。
多少の気持ち悪さを感じながら打ち始める。
すると木村の3000/6000が炸裂し、いきなりの親被りとなった。
何も出来ないまま、ただ点棒が削られていく展開に。
オーラス、木村の独走状態で70,000点オーバーとなっている。
こうなってしまっては着順を気にしてはおられず、早く終局させなければ木村の加点を
許すだけとなってしまうため、3着のままではあるが以下を木村から出アガり4回戦目を
自ら終わらせた。
南4局 1本場 ドラ






 ロン
ロン チー
チー

 チー
チー


ダブ南ドラ1の3900は4200で、着順は変わらずの3着で△23.7で終了。
5回戦
松本、柏井、岩崎、木村の並びスタート。
第1節の最後の半荘であるため何とかプラスで終わりたいという気持ちが招いた
中途半端な打牌が大惨事となり、今の自分の実力を物語る結果となった5回戦。
南3局 ドラ
親の岩崎からリーチが入る。
リーチを受けた直後の私の牌姿が以下のとおり。












 ツモ
ツモ
打 で聴牌となるが、
で聴牌となるが、 は通っていない。
は通っていない。
打 として、ドラの
として、ドラの と場に1枚切れの
と場に1枚切れの とのシャンポンでは、正直勝てる気が
とのシャンポンでは、正直勝てる気が
しなかった。よって理想系の 引きを考え、打
引きを考え、打 を選択する。
を選択する。
親の捨て牌を見るとチートイも否定できない河であったが、『通ってくれ』と
願いを込めて を打つ。
を打つ。
これが見事に親のチートイに突き刺さり、裏ドラも乗って18000の失点となった。
結局、この失点を取り返すことなど出来ず、ラスの△53.3pで5回戦目を終了した。
結果、第1節のトータルポイントは△45.8pであった。
******************************************************
5回戦目のインパチ放銃がかなりの衝撃でした。
今思うと本当に中途半端な1打だったと反省しています。
第1節目はプラスで終えたい気持ちがあり、そのため打 という『攻める姿勢』、
という『攻める姿勢』、
もしくは中抜きしてでも現物を切る『守る姿勢』、そのどちらも出来なかった
結果だと思います。
前回の自戦記で書きましたが、こうゆうところの『必死さ』が必要なんだと
感じます。
それが出来ない私のメンタルの弱さが、最も克服しなければならない課題だと
痛感しました。
(文:松本亮一)