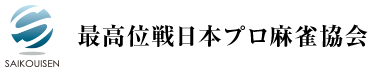2日目を終わって、首位を快走する佐藤と、最下位に甘んじている村上とのポイント差は300P余りに広がった。仮に3日目も差が縮まらない事態になると、村上の最高位の目は無い。
よく耳にする話として、トップ・ラスの順位点差60Pプラス素点差15Pくらいを考えれば、半荘1回で
75P余りは詰められ、3回もあれば200P以上の差が縮まるから、200Pくらい何てことないよ、という考え方。
あるいは、最終親番が終わらないかぎり、何万点差あろうと、逆転の目は残っているから、最終親番が終わるまではいつもと同じように打つ、という考え方。
どちらも理論上は正しいし、相手の思いもよらぬ心の乱れから、そのような考え方が日の目を見ることも稀にあるのだろうが、1%もある話ではない。
そもそもマージャンは、どんな考え方も表裏一体となっていて、レアケースを持ち出せば、あれもこれも間違ってない、それぞれが有り得る話になってしまう。
だからこそ、プロがそのあたりの思考や思想を提言し、交通整理する役割を担う責任があるのではないだろうか。にもかかわらず、1%も起こり得ない想定をして、実戦にまでその頼りない思考を投入してしまうのは、マージャンを愛してやまない人々を、思考のカオスに巻き込んでいく罪を犯していることに他ならない。
真の<勝負>とは、クライマックスで決するものではなく、それ以前の見落とされがちな局面で決しているケースが多い。
仮にクライマックスシーンで、もつれにもつれる展開になっているとすれば、それは四者の実力がよほど拮抗しているか、勝機を逸し合う凡戦の証しである。
前置きが長くなったが、村上が最高位の座を射止め、三冠の栄誉に輝くとすれば、この3日目に大量点を叩き出すしかないのである。
≪9回戦 南2局1本場≫ ←牌譜はこちら
ここまでの佐藤は、首位を突っ走る打ち手らしいスムーズさで、このゲームも取れそうなリズムでサイコロを振った。
そして、ワンズの1メンツとピンズの急所牌 をいとも簡単に引き込み、6巡のツモ中4巡が有効牌というリズムの良さでテンパイを果たす。
をいとも簡単に引き込み、6巡のツモ中4巡が有効牌というリズムの良さでテンパイを果たす。
そして即リーチ。













私はよく持ち点を馬力に換算してテンパイ形を眺める習慣がある。
たとえば3万点の原点が300馬力だとすれば、佐藤は404馬力でこの局を迎えたと考えるのである。もちろん、同じ持ち点でも上向きのエネルギーで迎えた局と、下向きのエネルギーで迎えた局の違いは当然ある。
従ってそこには補正が入るわけで、前局親満和了して今局に入っている佐藤は、私の目からは500馬力に近いエネルギーに見えた。
そういう視点で佐藤のテンパイ形を眺めると何か物足りない。
何が物足りないかと言えば、13枚中11枚がタンヤオ牌であるにもかかわらず、 のトイツだけが異質な部位になっている。
のトイツだけが異質な部位になっている。
役牌だから仕方ないじゃないかと考えることも可能だが、7巡目という早い段階で手にフタをするには、馬力余りになる不完全燃焼形に見えてしまうのである。
そしてもうひとつ。 の相方が
の相方が という不自然さ。これは数牌の性質の話として、3・5・7という数牌は、言わずもがなシュンツ作りのキーパーソンになっている牌たちで、シャンポン形という、シュンツ型の相方として役者不足の感は否めない。
という不自然さ。これは数牌の性質の話として、3・5・7という数牌は、言わずもがなシュンツ作りのキーパーソンになっている牌たちで、シャンポン形という、シュンツ型の相方として役者不足の感は否めない。
500馬力あたりでも、役牌と数牌のドラ無しシャンポン最終形になることもあるが、次のようなテンパイが自然に見える













佐藤の最終形との違いは、ワンズの →
→ トイツの
トイツの →
→ の3枚であるが、この3枚には重大な違いがあって、即リーチに踏み込むかどうかの核心だと私は考えている。
の3枚であるが、この3枚には重大な違いがあって、即リーチに踏み込むかどうかの核心だと私は考えている。
これは決して結果論ではなく、佐藤はリーチ2巡後に を引いているが、400余馬力のパワーがあれば当然の
を引いているが、400余馬力のパワーがあれば当然の で、
で、 を切ってのイーペー型リャンメン形リーチのほうが、エネルギーに見合ったリーチと言えるのである。
を切ってのイーペー型リャンメン形リーチのほうが、エネルギーに見合ったリーチと言えるのである。
仮に・・・という話はしたくはないが、佐藤がエネルギーに合った連荘をしていれば、次局の村上の6000オールも生まれていなかったわけで、マージャンは本当に紙一重の勝負の繰り返しで成り立っている。
≪9回戦 南3局≫ ←牌譜はこちら
≪10回戦 東3局1本場≫ ←牌譜はこちら
飯田が親倍を豪快にツモっている譜であるが、佐藤のリーチを受けて渋々 を残し
を残し をトイツ落とししているようにも見える。
をトイツ落とししているようにも見える。
佐藤のリーチが無ければ、飯田の手牌は7巡目にこうなっている














ここからの一打になるわけで、 ・
・ 共に1枚切れゆえ、自然に打
共に1枚切れゆえ、自然に打 と打ち、2巡後に
と打ち、2巡後に をアンコにして、
をアンコにして、 と
と のシャンポンでのリーチになっていたように思う。
のシャンポンでのリーチになっていたように思う。
佐藤のアガりに向かう執念はよくわかるが、前ゲームの9回戦で400余馬力あった位置から、終わってみれば3番手までズリ落ちた経緯を踏まえれば、ここはリーチを自重して欲しかった。205馬力には205馬力の処し方というものがあるはずだから。
≪10回戦 南1局≫ ←牌譜はこちら
栄華を極めた〔佐藤城〕陥落の絵巻である。
≪10回戦 南2局≫ ←牌譜はこちら
麻雀とは、敗れる者にとっては実に無惨で残酷なゲームである。
≪10回戦 オーラス≫ ←牌譜はこちら
極めつけはこの譜。
驚異の復活劇を果たす村上には、この日一日ずっと裏ドラの神様が付きっきりだった。(このあたりの話は、速報版でも吉田君が解説してくれているので、御参照あれ!)
裏ドラの神様は、そう簡単に近寄ってくれるものではなく、村上がマージャン牌たちと向き合う真摯さに惚れて、付きっきりになってくれたのではないかと私は思っている。
≪11回戦 東1局1本場≫ ←牌譜はこちら
村上の親リーと、飯田の押し返しに対し、安全牌に窮した佐藤が、配牌から抱えていた で放銃している。
で放銃している。
佐藤の手牌14枚の中から探せば、 よりも安全度の高い牌を見つけろというほうが、ムリな話に聞こえてしまうかもしれない。
よりも安全度の高い牌を見つけろというほうが、ムリな話に聞こえてしまうかもしれない。
でも前回戦、佐藤は箱下1万強のダンラスを引かされている。
佐藤ほどの打ち手であれば、自分の置かれている状況が、東1局とはいえ相当危ういものであることくらい、先刻承知のはず。
私は佐藤の類い稀な麻雀センスと、ふてぶてしいまでの勝負度胸の良さを買っている。そして<最高位>の座に就いても違和感の無いところまで力を付けてきている。だからこそ、つい辛口になってしまうのである。筆が滑ってしまうかもしれないが、許して欲しい。
飯田の捨て牌が異様である。
オーソドックスに手を進めるタイプの打ち手だけに、フェイクが入っているはずもなく、この捨て牌で親リーの一発目に無筋の をスッと切れるのだから、それなりの大役が入っていることは間違いない。
をスッと切れるのだから、それなりの大役が入っていることは間違いない。
普通に考えれば、七対子。もしくはソーズの一色手。もっと考えれば国士無双。チャンタ三色の手は、佐藤自身の手格好から考えにくい。
いずれにしても、親の現物である や
や には警戒感が必要で、だから佐藤は
には警戒感が必要で、だから佐藤は ではなく
ではなく のほうを選んだのだろう。恐らく七対子を本線に読んでいたはずで、少なくとも
のほうを選んだのだろう。恐らく七対子を本線に読んでいたはずで、少なくとも だけは切るつもりが無かったように思う。
だけは切るつもりが無かったように思う。
であれば、腹を括って を勝負してもよかったのではないだろうか。持ち点は開局なので3万点あったが、その半分の150馬力くらいしかない現状を踏まえれば、攻められた時に安全牌を探すようなヤワな考えは棄て、開き直りの一打を繰り出してもよかったように思う。
を勝負してもよかったのではないだろうか。持ち点は開局なので3万点あったが、その半分の150馬力くらいしかない現状を踏まえれば、攻められた時に安全牌を探すようなヤワな考えは棄て、開き直りの一打を繰り出してもよかったように思う。
≪11回戦 東2局1本場≫ ←牌譜はこちら
〔驕る平氏は久からず〕を地でいく放銃シーンである。
水巻のワンズ一色系に見える仕掛けに対し、(今のうち)とばかりに、 と
と をツモ切りして放銃しているが、謙虚に自分の置かれた状況を受けとめる<力>が欲しかった。
をツモ切りして放銃しているが、謙虚に自分の置かれた状況を受けとめる<力>が欲しかった。
攻める<力>が強過ぎると、受ける<力>が弱くなるのが普通で、今局の佐藤はまさに普通の打ち手。
自分の間合いで打てなくなる時間帯であることは知っているはずなのに、ついつい前傾姿勢が前のめりになり過ぎて、視界が極端に狭まり放銃してしまう佐藤。
せっかく水巻が ポン→打
ポン→打 としてくれたのだから、
としてくれたのだから、 をツモ切りせずに
をツモ切りせずに を合わせ打ちして<受け>に入るのがプロフェッショナルな対応というものだ。自分の手牌がイーシャンテンやテンパイになっている時ほど、仕掛けが入って掴まされた牌はツモ切りしないのが、150馬力の鉄則である。
を合わせ打ちして<受け>に入るのがプロフェッショナルな対応というものだ。自分の手牌がイーシャンテンやテンパイになっている時ほど、仕掛けが入って掴まされた牌はツモ切りしないのが、150馬力の鉄則である。
≪11回戦 東3局≫ ←牌譜はこちら
今度はマンガン放銃シーン。
前局に引き続いて主役は佐藤である。
佐藤は村上からリーチがかかる直前にこの手牌から を切っている
を切っている














通常なら 切りで良いことくらい佐藤だって百も承知。にもかかわらず
切りで良いことくらい佐藤だって百も承知。にもかかわらず に手をかけたのは、<受け>を考えてのこと。もちろん、すぐに
に手をかけたのは、<受け>を考えてのこと。もちろん、すぐに が出てくれば、ポンテンの速攻をかけ、体勢を立て直す目論見でいたはず。
が出てくれば、ポンテンの速攻をかけ、体勢を立て直す目論見でいたはず。
ところがすぐに村上からリーチがかかってしまい、ちょっと予測より早いが、 をトイツ落としして凌ぎにかかる佐藤。
をトイツ落としして凌ぎにかかる佐藤。
そして放銃の10巡目、この手組みから、カン を打牌に選んでしまう佐藤。
を打牌に選んでしまう佐藤。














 が通っていて
が通っていて が4枚見えているから、
が4枚見えているから、
 待ちが無く、ならば自分の手組みをカンチャンにせずリャンメンにしておこうと、さして迷うこともなく
待ちが無く、ならば自分の手組みをカンチャンにせずリャンメンにしておこうと、さして迷うこともなく を選んでしまう佐藤。
を選んでしまう佐藤。
でもこの放銃、不運で片付けてよいものだろうか。丁寧に現物の を切って我慢強く打つ1局だったのではないだろうか。
を切って我慢強く打つ1局だったのではないだろうか。
調子が落ちてくると、今局のように思いもよらぬ放銃をしてしまうものだ。そういう不幸なシーンに出食わさぬよう、調子が落ちる前に準備しておくもので、佐藤がそんなことも知らぬはずがない。
だからこそ、今局のような危うい局は、いつもの何倍も慎重に一打一打選んでいかなければならないのである。
この放銃で、佐藤は前回戦に続いて箱テンのラスを引き、たった半荘2回で、2日目までの貯金をすべてはたいてしまったのである。
≪11回戦 東4局2本場≫ ←牌譜はこちら
9・10回戦に連勝し、勢いに乗る村上のトイトイ和了譜である。
10回戦までの村上を見ているかぎり、ほとんどの手牌をリャンメン形テンパイに持ち込む手筋を用いていて、もしかしてトイツ系の手筋は意識的に否定しているのかな?と思っていたが、今局は別人のような手筋は駆使している。
2巡目、村上の手牌はこうなっていた













ここへ北を引いて 、
、 を引いて
を引いて と打っていっている。
と打っていっている。 がドラであることも含め、私はこのトイツ手筋に驚愕してしまった。
がドラであることも含め、私はこのトイツ手筋に驚愕してしまった。
そして目論見どおり と
と を重ねた村上は
を重ねた村上は をポンしてトイトイに向かう。ただその時点で
をポンしてトイトイに向かう。ただその時点で は飯田と持ち持ちになっていた。
は飯田と持ち持ちになっていた。
そして ポンの次巡、水巻からリーチがかかる。そのときの飯田の手牌はこうだった。
ポンの次巡、水巻からリーチがかかる。そのときの飯田の手牌はこうだった。













タンヤオ七対子のイーシャンテンである。水巻のリーチさえ無ければ何も問題が発生しなかったのだが、熾烈なトップ争いを村上と繰り広げている飯田としては、放銃しての後退は避けたかったので、 のトイツ落としをかけていく。
のトイツ落としをかけていく。 が4枚見えているし、水巻自身も
が4枚見えているし、水巻自身も を切っているため、シャンポン待ちは99%無い状況を読んでの
を切っているため、シャンポン待ちは99%無い状況を読んでの 切りだった。
切りだった。
しかも珍しく村上がトイツ手筋に入っていたため、4巡目の村上の 切りも飯田にとっては盲点になる一打となっている。
切りも飯田にとっては盲点になる一打となっている。
持ち持ちの数牌がポンできる時は間違いなく好調で、飯田もビックリの村上和了シーンだったに違いない。
≪11回戦 南2局3本場≫ ←牌譜はこちら
この譜を掲載するかどうか迷ったが、佐藤のために載せることにした。
負ける日は、こういう譜が生まれるものだが、<最高位>に就く打ち手は、できるかぎり負ける日の譜に神経を注いで欲しいという願いをこめて載せてみた。
≪12回戦 東1局≫ ←牌譜はこちら
飯田はこの12回戦を迎えてトータル首位に立っていた。佐藤の自爆もあるが、全20回戦の後半に入って、飯田自身の予測よりかなり早く首位に立ったことに、果して違和感は生じていたのだろうか。
そしてその開局、飯田は譜の配牌から、第1ツモ →打
→打 と打っていった。
と打っていった。
ところが・・・この打 を見て、「これで飯田さんの三連覇は無いよ」と看破した男がいた。最終日こそ不在だったが、ほとんどの対局を食い入るように見ていたその男は、確信に満ちた表情で更に続けて話してくれた。
を見て、「これで飯田さんの三連覇は無いよ」と看破した男がいた。最終日こそ不在だったが、ほとんどの対局を食い入るように見ていたその男は、確信に満ちた表情で更に続けて話してくれた。
「この配牌からの第1打は しかないだろ。土田は字牌から切らないから
しかないだろ。土田は字牌から切らないから なんだろうけど、飯田さんが
なんだろうけど、飯田さんが を選ぶなんて・・・おかしいだろ」
を選ぶなんて・・・おかしいだろ」
確かに、飯田の第1打をひもといてみても、これだけ充実したタンピン系の配牌から、 より先に
より先に を選ぶ飯田を見たことがない。
を選ぶ飯田を見たことがない。
だが、その一打を見て飯田の優勝を完全否定してしまう(しかもその表情は怒りに充ちていた)男の真意はどこにあるのだろうか?
飯田は第1打に を切った次巡、イーペーコーが完成する
を切った次巡、イーペーコーが完成する を引いて
を引いて を切っていく。そして次巡また
を切っていく。そして次巡また を引くと打
を引くと打 としている。
としている。














 をツモ切りする手もあったが、ピンズの受けを増やす
をツモ切りする手もあったが、ピンズの受けを増やす 切りは自然な一打だった。
切りは自然な一打だった。
ところが、この 切りで飯田の手牌は一手遅れの軌跡を辿ってしまう。
切りで飯田の手牌は一手遅れの軌跡を辿ってしまう。
仮にイーペーコーを確定させておく ツモ切りとしておくと、次巡のツモ
ツモ切りとしておくと、次巡のツモ で打
で打 となり、6巡目のツモ
となり、6巡目のツモ でイーシャンテンに構えられる
でイーシャンテンに構えられる













そして次巡ツモ で七対子イーシャンテンとなり、
で七対子イーシャンテンとなり、 もしくは
もしくは 、どちらを切っても、9巡目のドラ引きでテンパイを果たし、
、どちらを切っても、9巡目のドラ引きでテンパイを果たし、 もしくは
もしくは 待ちとなる。
待ちとなる。
6000オールを仕留めた村上の11巡目の 、13巡目の
、13巡目の が、飯田の切り順にかかわらず打ち出されてくる牌なので、3巡目の
が、飯田の切り順にかかわらず打ち出されてくる牌なので、3巡目の 切りが悔やまれる飯田であった。
切りが悔やまれる飯田であった。
ただ、それ以前の大きな問題がこの局にはあるわけで、村上が最終ツモでツモり上げた と、飯田の第1打の
と、飯田の第1打の の因縁がこの局を境に始まっていくのであった。
の因縁がこの局を境に始まっていくのであった。
飯田が十度も最高位の冠を戴き、永世最高位の勲章を手に入れることができた最大の功労者は、紛れもなく金子正輝である。これは皮肉でも何でもなく、金子という好敵手の存在があればこそ、飯田が映えたのである。
お互いのすべてを知り尽くしている好敵手ゆえ、「飯田さんの目は無い」と言い切れたのである。それも、東1局の第1打牌 を見ただけで、言い切れたのである。
を見ただけで、言い切れたのである。
『強者は強者を知る』を地でいくような発言で、その説得力に私は脱帽してしまった。
金子の真意を説明すると、残り半荘9回戦あるにもかかわらず、楽をして勝とうというか、少しでも安全なところに身を置いて勝ちを拾おうとする心理が、第1打に を選ばせなかったのではないか?と金子は分析したのである。
を選ばせなかったのではないか?と金子は分析したのである。
安全牌化しやすい を手元に置くということは、そういうことであり、第2ツモの
を手元に置くということは、そういうことであり、第2ツモの で気を取り直して打ち出したものの、飯田らしからぬ1巡の温存に、金子は9回戦先の姿を見てとったのである。
で気を取り直して打ち出したものの、飯田らしからぬ1巡の温存に、金子は9回戦先の姿を見てとったのである。
本物の<勝負>、本物の<修羅場>を数多く経験してきた男の慧眼に、私は感服してしまった。
<勝負>は<ゲーム>ではない。その違いを知っているプロは少なく、ともすれば<ゲーム>感覚で打ち合うシーンが多くなっている現代マージャンでは、金子の言葉と思考は昭和の形見になってしまうのだろうか。
≪12回戦 東2局≫ ←牌譜はこちら
見事にコーツ場の流れに乗った水巻の三暗刻和了図である。
こういう譜を見てつくづく思うのだが、ドラが でなければ、もしかするとテンパイにとらない打ち手もいるだろうなと。
でなければ、もしかするとテンパイにとらない打ち手もいるだろうなと。
そして10巡目のツモ でテンパイになり、次の形でリーチをかけるのだろうなと。
でテンパイになり、次の形でリーチをかけるのだろうなと。













譜をご覧いただければわかるように、この段階で和了牌の と
と は3枚生きている。
は3枚生きている。
四暗刻成就の定番となっている、尖張牌アンコ論からいけば、八割方水巻のツモ筋に は眠っているはずだ。
は眠っているはずだ。
暴論に聞こえるかもしれないし、現実にはドラが なのだから、この倍満和了図以外の想定を考えるほうがおかしいと言われるかもしれない。でもマージャンは、アガりがあった後にもドラマが隠されていることを忘れてはならないように思う。
なのだから、この倍満和了図以外の想定を考えるほうがおかしいと言われるかもしれない。でもマージャンは、アガりがあった後にもドラマが隠されていることを忘れてはならないように思う。
水巻はこの倍満和了で今回戦トップを取り、3日目をプラスで打ち終える。
そして最下位を迷走していた村上が大勝し、首位を快走していた佐藤が大敗したため、首位は水巻に替わり、最下位村上との差は、たった50Pほどになってしまった。
50P差はあって無いような超僅差。文字通り横一線の戦いになるわけだが、金子の予言がどうも気になって仕方がない。
そして戦いはいよいよ佳境に入っていく。