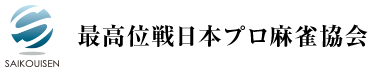年を取ってから、20代30代の頃とは違って睡眠にさく時間がとても少なくなってきた。
日々4~5時間ぐらいかな。丸一日起きていた後でも、それ以上続けて眠れない。 あとの20時間近くを、多少の仕事(?)と家事(?)に使うが、大半は趣味のマージャンと読書に費やされる。
まず読書のほうでは、好きな傾向のものを生理的に選んでいくことになるが、時にどうしても、難解ということではなく、ぼくのうちにできている、「小説」 「文学」という構図にあてはめることが出来ず、立ちつくしてしまうような作家に出会うことがある。
安部公房がその代表例だ。作家には読者に受け入れてもらいたいという欲求があるはずなんだが、一向にそんなことには頓着せず、ひらすら自分の世界を構築していく。まるで砂丘に忽然と立てられたコンクリートの構造物のようだ。どこにでも出入口が見つからず、そうなると砂丘を悄然とした足取りで 、引き返し、住み慣れた地にもどり、安心できる作家達(色川、漱石、太宰)などに囲まれて過す・・・・
マージャンにおいて、ぼくが打っている時、頭によぎることは、分岐点、重要と思える局面で、長年見続けてきたAリーグ選手達のことだ。例えば、金子だったらどう捉えてどう対処するだろうか、村上だったらメンゼンで貫き通すだろうか、石橋ならひとつ動いて場を展開させていくかな、など。
もちろんレベルの違いは自覚してはいるが、そんな風に考えて楽しんだりしている。
石井一馬の出現が、今まで小説とは、いや間違い(!?) マージャンとは、こんなものだろうと勝手に思い込んできたぼくを驚かせてくれたが、もうひとり、ずーっと驚かされ続けている打ち手がいる。平賀聡彦だ。
同じ驚きといっても一馬とは正反対だ。一馬は局面を見渡し、どのような事態にも対応してみせる自信を持ちつつあるが、平賀は逆に相手三人に自分への対応をせまっていくように思える。
実際に話してみても、「相手に対応させ、自分が曲げない」とのこと。その曲げなさぶりは、イヤという程見せられてきた。そこまで一徹な打ち手は他にいない。たった一人の流派だ!そう感じていることを本人に伝えてみると、「自分としては、飯田、張の流れを汲む打ち手である、ありたい」とのこと。
ひとつひとつの事象、局面に反応していくのではなく、大局的に全体像と対峙していくという点ではうなずけるが、ぼくの印象では先にあげてくれた飯田、張のゆったりとした姿勢とはあきらかに違う。あと、似ているかなぁと、女流永世最高位・根本の名をあげていたのも面白い。
さて具体的に譜を追ってみよう。
(第38期第4節B卓2回戦東2局1本場)

遅い仕上がりながら、ドラ  ツモで
ツモで
 ツモで
ツモで












 から打
から打 
2巡後ツモ  で4000オール。
で4000オール。
 で4000オール。
で4000オール。打  だと456の三色完成形の
だと456の三色完成形の 
 待ち。だが佐藤にその
待ち。だが佐藤にその  をチーされ、
をチーされ、 と
と  シャンポン待ちに。さすがに次巡喰い取った
シャンポン待ちに。さすがに次巡喰い取った  でヤメるだろう。8000オールまで見込める手組みもテンパイ料どまり。
でヤメるだろう。8000オールまで見込める手組みもテンパイ料どまり。
 だと456の三色完成形の
だと456の三色完成形の 
 待ち。だが佐藤にその
待ち。だが佐藤にその  をチーされ、
をチーされ、 と
と  シャンポン待ちに。さすがに次巡喰い取った
シャンポン待ちに。さすがに次巡喰い取った  でヤメるだろう。8000オールまで見込める手組みもテンパイ料どまり。
でヤメるだろう。8000オールまで見込める手組みもテンパイ料どまり。ぼくは手役狙いだけではなく、多面張を捨てても両面に取ってしまいそうだ。(サンマのやりすぎかな?)
確かに下家の佐藤が仕掛けてどうみてもピンズ模様。
 どちらを選んでもリスクはある。ぼくなら牌理上の手クセで、平賀なら手役、手格好から打
どちらを選んでもリスクはある。ぼくなら牌理上の手クセで、平賀なら手役、手格好から打  だろうと思っていたので意外な気がしたのを覚えている。
だろうと思っていたので意外な気がしたのを覚えている。

 どちらを選んでもリスクはある。ぼくなら牌理上の手クセで、平賀なら手役、手格好から打
どちらを選んでもリスクはある。ぼくなら牌理上の手クセで、平賀なら手役、手格好から打  だろうと思っていたので意外な気がしたのを覚えている。
だろうと思っていたので意外な気がしたのを覚えている。譜を見ながら振り返ってもらったら、危険度では打  のほうが多少高いように思えるが、その対応としてだけではなく、ピンズ以外の待ちを含むほうが、有利で、
のほうが多少高いように思えるが、その対応としてだけではなく、ピンズ以外の待ちを含むほうが、有利で、
 の感触が良かったとのこと。
の感触が良かったとのこと。
 のほうが多少高いように思えるが、その対応としてだけではなく、ピンズ以外の待ちを含むほうが、有利で、
のほうが多少高いように思えるが、その対応としてだけではなく、ピンズ以外の待ちを含むほうが、有利で、
 の感触が良かったとのこと。
の感触が良かったとのこと。もうひとつ取り上げてみよう。
(第38期第4節B卓4回戦東2局)

9巡目、佐藤のリーチを受けて、テンパイと一発消し両方かなう  チー。2000点の
チー。2000点の  バックだ。
バックだ。
 チー。2000点の
チー。2000点の  バックだ。
バックだ。ところが次巡、他三者に対してかなり打ちにくい  ツモ。さすがの平賀も
ツモ。さすがの平賀も のトイツ落とし!2巡後またしても
のトイツ落とし!2巡後またしても  ツモ 打
ツモ 打  でフリテンの
でフリテンの 
 スジシャンポンに。おまけに親の新井が、ドラ切りとはいえ、ドラまたぎ間四ケンの
スジシャンポンに。おまけに親の新井が、ドラ切りとはいえ、ドラまたぎ間四ケンの  まできている。ところがリーチ者の捨て牌
まできている。ところがリーチ者の捨て牌  を見ながら、なんと
を見ながら、なんと  をツモりきってしまう。もう漫画みたいだね(失礼!)
をツモりきってしまう。もう漫画みたいだね(失礼!)
 ツモ。さすがの平賀も
ツモ。さすがの平賀も のトイツ落とし!2巡後またしても
のトイツ落とし!2巡後またしても  ツモ 打
ツモ 打  でフリテンの
でフリテンの 
 スジシャンポンに。おまけに親の新井が、ドラ切りとはいえ、ドラまたぎ間四ケンの
スジシャンポンに。おまけに親の新井が、ドラ切りとはいえ、ドラまたぎ間四ケンの  まできている。ところがリーチ者の捨て牌
まできている。ところがリーチ者の捨て牌  を見ながら、なんと
を見ながら、なんと  をツモりきってしまう。もう漫画みたいだね(失礼!)
をツモりきってしまう。もう漫画みたいだね(失礼!)採譜をしながら、頬をゆるめたのを覚えている。
超危険に見える(実際は誰にも無関係)  を強打して、
を強打して、 バックを和了りきるのと、フリテンシャンポンに組み直してツモ和了るのと、いったいどちらが平賀らしいんだろうね!?(個人的には
バックを和了りきるのと、フリテンシャンポンに組み直してツモ和了るのと、いったいどちらが平賀らしいんだろうね!?(個人的には  叩き切って
叩き切って  で和了るほうを見たかったかな。)
で和了るほうを見たかったかな。)
 を強打して、
を強打して、 バックを和了りきるのと、フリテンシャンポンに組み直してツモ和了るのと、いったいどちらが平賀らしいんだろうね!?(個人的には
バックを和了りきるのと、フリテンシャンポンに組み直してツモ和了るのと、いったいどちらが平賀らしいんだろうね!?(個人的には  叩き切って
叩き切って  で和了るほうを見たかったかな。)
で和了るほうを見たかったかな。)38期決定戦におしいところで届かず、ニコニコしながら、「フミさんがコラムでぼくのこと書いてくれないから、ダメだったじゃないの」と苦情!!
さぁ、もう取り上げたよ。今期は決定戦で会おうね。
“