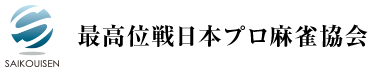「マスター、ちょっと打っていてよ」
そう言ってトイレに立った。
特別便意を催したわけではなかったが、少々頭を冷やす時間が欲しかったのだ。
トイレの窓を思い切り開けると、深夜の冷気がほてった顔を撫でる。
それだけでも、少し正気に戻ったような気がした。
(フゥー、しかしどうしてもイカンな)
開始してから7時間、今だに悪いときの典型的な状態が続いている。
たった今、ドンさんに放銃った一打にしてからがそうで、まるで悪いときの見本をみているようだった。
私の方には、珍しく早い巡目に好形のテンパイが入っていて、











 ドラ
ドラ 抜きドラ
抜きドラ



このテンパイをしたのが5巡目、さすがにこの局はテンパイ一番乗りという自信があった。
2人の捨牌にはまだテンパイ気配は感じない。よほどリーチといって2人の手を止めようかとも考えたが、結局はダマテンの方を選んでいた。
私の方は十分形と考えてもいいような手牌であり、少なくともマチは
 から変化しそうもない。それだけに、リーチをかけてみる手段も十分成立しそうな気もするのだが、それでもダマテンにしたのはふたつばかり理由がある。
から変化しそうもない。それだけに、リーチをかけてみる手段も十分成立しそうな気もするのだが、それでもダマテンにしたのはふたつばかり理由がある。
ひとつは、リーチごときで手牌を曲げてくれる相手ではないこと。ということは、
 が不要牌のときに打ち出される巡目が遅れる分だけ不利と考えられる。その間にもう一方にアガられるチャンスが増えるからだ。
が不要牌のときに打ち出される巡目が遅れる分だけ不利と考えられる。その間にもう一方にアガられるチャンスが増えるからだ。
一局の勝負ではない、この勝負が終るまでの一過程なのだ。
高くアガることなどは一切考えていない。
いかにしてアガリ切るかが問題なのだ。
もうひとつ気になったのは、トド松の仕掛け。3巡目に をポンして、捨牌は、
をポンして、捨牌は、




テンパイまではいっていないという気はしたが、好形の一シャンテンは間違いないだろう。

 とペンチャンを落してきた後に、
とペンチャンを落してきた後に、 が捨てられており、さらに初牌の
が捨てられており、さらに初牌の が手出しで打たれてきた。
が手出しで打たれてきた。
捨牌だけで読んでもそうなのだが、それよりも、現在の状態を比較すると、こちらにだけ好形のテンパイが入り、相手の手牌が遅いなどということは考えづらい。
ダマテンにしたのは、この好形の一シャンテンに対して注意を払った意味もある。
7巡目に私が引いたのは 。
。













ここで をツモ切る人がいたら麻雀をやめた方がいい。
をツモ切る人がいたら麻雀をやめた方がいい。
では何を切るかというと、 を切る。
を切る。
タンヤオと高目イーペーコを捨てるのだ。
これがこの局面、対トド松だけを考えれば最善手。
4人麻雀ならば、9分9厘切る 。
。
それなのになぜサンマーでは の方を切らなければならないか。
の方を切らなければならないか。
簡単な話だ。 の方がポンが入りづらいからだ。
の方がポンが入りづらいからだ。
ドンさんの方にまだテンパイが入ってないと思ったならば、トド松の手牌を進ませない方がいいに決まっている。
ここが同じ麻雀でもサンマーと4人麻雀の大きな違いで、4人麻雀では半荘という目処が一応はあるが、サンマーにはそれがない。
半荘の勝負を争うのと、ツキの取りっこを争うのとではこれだけ違うのだ。
さらに、4人麻雀ではタンヤオとイーペーコの2翻が付けば得点が4倍になる。
半荘の勝ち負けを争うのならこれは大きな魅力で、 を打たないのではそれこそ麻雀を打つ資格がない。
を打たないのではそれこそ麻雀を打つ資格がない。
ところがサンマーの場合は、2翻が付いたとしても4倍になるわけではなく2点増えるだけのことなのである。
たとえば、同じ でアガったとしても、
でアガったとしても、 を切った場合は、ピンフ1点、ドラが1点と場ゾロで4点、それに抜きドラが4枚で計8点。それが
を切った場合は、ピンフ1点、ドラが1点と場ゾロで4点、それに抜きドラが4枚で計8点。それが を切った場合でも10点にしかならないのだ。
を切った場合でも10点にしかならないのだ。
たったそれだけのことでトド松の手牌を進ませ、アガれる手をアガれなくさせてしまったりしたら、その後何百点の損になるか分からない。特にこの2人相手ならなおさらだ。
1度でもそんなことをしたらもう取り返しがつかないことになる。
ただし、サンマーのセオリーだからといって、普通の麻雀にまるっきり役に立たないかというと、そんなことはない。
サンマーというのは麻雀の原点のようなもの、4人麻雀のセオリーを教えてくれるところが随所にある。
たとえば、私の手牌がオーラスのトップめのものだとする。そして、トド松に千点アガられるとトップは逆転されてしまう。
そういった局面ならばどうするか。
当然 の方を切る。
の方を切る。
念を押すまでもないが、トド松にはカン というマチはないのだ。
というマチはないのだ。

 という形ならば
という形ならば より先に
より先に を切っている。
を切っている。

 でアタるのならどちらを切っても同じ、
でアタるのならどちらを切っても同じ、 と
と のどちらがポンが入りやすいかも一目瞭然だ。
のどちらがポンが入りやすいかも一目瞭然だ。
まさか、こういう状態のオーラスのトップめがタンヤオやイーペーコーに目が眩んだりすまい。こんなもの迷わず を切らなくちゃいけない。
を切らなくちゃいけない。
ところが、このへんが不ヅキの典型といえるところで、この が、まさかのドンさんにアタってしまったのだ。
が、まさかのドンさんにアタってしまったのだ。
ドンさんの手牌は、











 抜きドラ
抜きドラ




門前1点、七対子2点、ドラが2点のバンバン(場ゾロ)で計7点、抜きドラが5枚で合わせて12点。
さほど点数は高くないが、そんなことは問題じゃない。
単騎の仮テンにジャストミートさせてしまったということが、現在の状態をよく表しているのだ。
それでもたったひとつの救いは、この絶望的な状態を認識していることだ。
ここまできたら意地でも退くわけにはいかないが、この状態を認識しているのとしていないのとでは大差がある。ハズミやツキで挽回できるような相手ではないのだ。
ここで熱くならずトイレに立つことができるというのは、実は大変なことなのである。
──それしかテンパイのとれない 単騎とそれしか打ちようがない
単騎とそれしか打ちようがない か……、絶望的だな。
か……、絶望的だな。
夜の冷気にあたりながら、冷静になって考えてみても、どこにも間違いはないという自信があった。
7時間の大半は、そういったようにミスを打たないことだけに費やされてきたのだ。
しかし、それでも相手はミスをしない。
初っ端の私の 打ちのミスで開いてしまった差がいっこうに縮まらないだけなのだ。
打ちのミスで開いてしまった差がいっこうに縮まらないだけなのだ。
ただ、それだけにこの局面を力でなんとかしたいという気持ちも強い。
自分の麻雀に対する自信を試してみたいのだ。
(よし、もう少しガンバってみるか)
そう気合いを入れて、トイレを出た。
マスターになんとかしてもらおうなどという気持はまったくなかったのだが、戻ってみるとリーチがかかっていた。
が、そのリーチを見てガッカリした。











 ドラ
ドラ 抜きドラ
抜きドラ




こんなリーチはない。
リーチをかけてもかけなくても ならばアガれるのだ。
ならばアガれるのだ。
しかも、この手牌、リーチをかけなければ手変りが十分考えられる。 を引いての
を引いての





 、あるいは
、あるいは を引いての
を引いての





 。
。
こうなってからリーチで十分なのだ。
あわててリーチをかけてしまえば、この変化はない。
おまけに はドラであり、出アガるなら
はドラであり、出アガるなら の可能性が高いが、
の可能性が高いが、 で出アガるのならヤミテンでも1点しか違わない。
で出アガるのならヤミテンでも1点しか違わない。
いかにアホらしいリーチかが分かる。
案の定、それから数巡後 をツモ切っていた。
をツモ切っていた。
(何を考えて麻雀を打っているんだ、マスターは)
そうは思ったが、いつも負け組のマスターにそこまで要求するのは酷というものか、まあどうせこの一局は捨てた一局。次戦からは心機一転ガンバればいいだけだ。
そう思わずにはいられなかった。
局面は進んでいたが、まだ決着がつかなかった。
マスターがアガれないのは分かるが、他の2人も手が遅いのだろうか。
そうすると はモチモチか、これはマスターのアガリはないな。
はモチモチか、これはマスターのアガリはないな。
しかし不思議なことに

 の方も出もしなければツモリもしない。
の方も出もしなければツモリもしない。 は一枚切れているが、残りはどうしたのだろうか。
は一枚切れているが、残りはどうしたのだろうか。
考えられるのは対子場。
対子場の時は大物手も出やすいが、この局のように局面が遅くなることがある。
私はドリンクを取りにいくふりをして、2人の手を覗いた。
覗いた瞬間(オッ)と思った。
ドンさんの手牌が、












だったのだ。
そして、トド松の手牌が、












なのだ。
やはり対子場になっている。それも、驚いたことに

 は1枚も山に生きてはいないのだ。
は1枚も山に生きてはいないのだ。
しかも、 はモチモチになっておらず、2人に1枚づつ。
はモチモチになっておらず、2人に1枚づつ。
2人がアガリにかけても を持っている限りアガリはないのだ。
を持っている限りアガリはないのだ。
トド松の方はわからぬが、ドンさんの方はテンパイすれば十中八九打ち出されるだろう。
私がドリンクを持って戻ってくると、ちょうどドンさんが を引いたところだった。
を引いたところだった。
「ローン!モチモチかと思ったよ」
マスターが、そう言いながらアガった。
門前1点、ドラが2点、 が1点、リーチが1点、それに裏ドラが
が1点、リーチが1点、それに裏ドラが で3点のバンバンで計10点。
で3点のバンバンで計10点。
それに がセット(4枚揃うこと)で倍の8点、
がセット(4枚揃うこと)で倍の8点、 が1点で計9点。
が1点で計9点。
合わせると19点。ちょっとしたアガリだ。
(なるほどね、こういったこともあるのか)
そう思わずにはいられなかった。
落ち目の時には当り前に打ち合っても、相手の方が一歩だけ早い。
たまにはこういった具合いにセオリー外しをやらなければキッカケを掴めないのかもしれない。
(だが、オレはやらんだろうな)
そうも思った。
どんな局面でも奇襲戦法になんか頼らず、地力だけで戦いたい。
麻雀に対する自信がそうさせるのだが、ちょっとやそっと不利になったからといって、奇襲戦法で流れを変えようなんてことを考えているのでは本当の地力は身につかないと思っているからだ。
この局面が対子場と読み切っていても、私ならダマテンから

 マチに変化させているだろう。
マチに変化させているだろう。
そして、今の状態から、 が打ち出されるのは
が打ち出されるのは

 に手変りしてリーチをかけた後なのは間違いない。
に手変りしてリーチをかけた後なのは間違いない。
その結果は

 の純カラ、2人への放銃だろう。
の純カラ、2人への放銃だろう。
そんな局面が何度もあった。
それでも、リーチはかけないに違いない。
それで勝てるという自信があるからだ。
だが、この日に限っては、明らかにこれがキッカケになった。
代わってすぐ、こんな手をテンパイ。











 ドラ
ドラ 抜きドラ
抜きドラ

3巡目と早いが、これはリーチをかけるよりしかたがない。
このリーチに対しての対応がこれまでとは少し違ったのだ。
まず、トド松の一打目が2枚切れの 、2打目が現物の
、2打目が現物の 。そしてドンさんは
。そしてドンさんは の対子落し。明らかに2人の手が遅いのだ。
の対子落し。明らかに2人の手が遅いのだ。
こんなときは、むやみに放銃して私に勢いづかせたくないもの。局面が長びけばツモる可能性も高くなる。
(これはツモアガれるかもしれないぞ)
そう思った瞬間、意外にもアッサリとペン をツモアガった。
をツモアガった。
それからだった──。
“