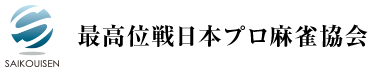私はドロ沼の中にいた。
もがけばもがくほどドロ沼に足を捕られて身動きができなくなっていく、そんな感じさえするほど状態は最悪だった。
サンマーの王者トド松、怪物ドンさん、この二人を相手に始まったサンマー勝負、相当厳しいモノになることは予想していたが、まさか最初からこれほどの劣勢になろうとは………。
確かにこの二人、半端じゃないほど強い。
私のシマ内ではNO1、NO2を争うが、おそらくは、日本中を探しても有数の打ち手に違いない。
その二人を相手に1度でもツキを落としてしまえば、どんな悲惨な状態になるかは見当がついていたはずだ。
二人にとっても同じことで、1度落としたツキを元の状態に押し戻すのは並大抵の苦労ではない。だから三人共が、出だしはツキの行方に相当な神経を使う。
この序盤戦のかけひきが、実はサンマーの醍醐味であって、1度相手とのツキに差をつけてしまえば、後は勢いに乗って打てる。そうなるまでが勝負といってもいいくらいなのである。
ところが、そのことを熟知している者同士の対戦になると、なかなかツキの取りっこに決着がつかない。ましてや、ドンさん、トド松、そして私の対戦ならば、序盤戦だけに終始してしまうのではないかと思うぐらい、序盤戦が長く続くと思っていた。
それほどこの三人は実力が接近し、簡単に誰かがツキを落としてしまうなどとは、誰も考えていなかった。
ところが、まるでこの序盤戦を省略してしまったかのように、私がいきなりツキを落としてしまったのである。
序盤戦の微妙なかけひきには、ほんのささいなことが大きく影響してくる。そう考えると、
「サンマーじゃ金子君とサシウマはいけないな。どうだ1本でやろうじゃないか」
と言われたのが影響しているようにも思う。
自分ではもちろん、そんなことで揺れるはずはないという自信はあった。
確かに1本というレートは、今まで打ったことのないキツイレートなのだが、卓に着いた以上はレートがいくらであろうと関係なく、ツキの取りっこでしかないと覚悟を決めていたはずだ。
しかし、私は始める前に躊躇している。それはそうだ、いきなり1本といわれれば即座に返答なんかできっこない。
その微妙な気持の揺れが、ドンさんの狙いだったのか、それとも、こんなものどうってことはないよ、というところを見せつけ私を圧倒しようというのが狙いだったのか。
最初はほんの些細なことだった。
始まると同時に、トド松がいきなり をポン、と仕掛けた。私の手牌は、
をポン、と仕掛けた。私の手牌は、













いきなりの ポンに対して、初牌の
ポンに対して、初牌の

 を切り出すのはイヤだ。
を切り出すのはイヤだ。
かといって、この3枚を絞り切ってしまうのは、普通の麻雀の感覚であって、この麻雀はもっと微妙だ。絞るだけでもツキを落とすし、切るのが早過ぎても相手を勢いづかせてしまう要因になる。
トド松の第1打は 。
。 をポンして
をポンして を切ったからといって、混一と決めつけるのは早計で、役牌暗刻、先ヅケ、対々やチャンタ(このふたつの可能性は極めて少ないが)、なんだってある。
を切ったからといって、混一と決めつけるのは早計で、役牌暗刻、先ヅケ、対々やチャンタ(このふたつの可能性は極めて少ないが)、なんだってある。
トド松の手牌が役牌暗刻で1翻が確定している場合は、絞ったためにスピードで遅れをとってしまうし、先ヅケだった場合は、それをポンしなければアガれない手牌を楽に進ませてしまうのだから、できればトド松に対子の役牌は最後に捨てたい。
この兼ね合いが実に難しい。
私はあの手牌にツモ で
で と打った。
と打った。
つまり、トド松の手牌を進ませない方を選んだ。この不十分形から、バラバラと初牌を打っていくのは、無謀に思えたからなのだが、打 と一呼吸置くのも、ひとつの手段であって、
と一呼吸置くのも、ひとつの手段であって、 打ちの時点ではどちらが正解手なのか判別するのは非常に困難だった。
打ちの時点ではどちらが正解手なのか判別するのは非常に困難だった。
 打ちの2巡後ツモ
打ちの2巡後ツモ 。
。
このときになって、しくじったか、とも思ったが、初牌3枚を切り出せばトド松に動かれたかもしれず、ならこのツモはない。
だが、とりあえず 打ち。
打ち。
ポンは入らなかった。
そしてツモが 。
。













こうなると が痛い。それでも一応一シャンテン、これで初牌ふたつを絞るのでは、このルールのサンマーでは緩手になる。
が痛い。それでも一応一シャンテン、これで初牌ふたつを絞るのでは、このルールのサンマーでは緩手になる。
ちょっと嫌な気がするが を打った。
を打った。
と、これにも動きが入らない。こうなってくると、ますます 打ちが緩手に思えてくる。
打ちが緩手に思えてくる。
そしてツモが 。
。 の引き戻しがあり、ちょっと迷ったが、
の引き戻しがあり、ちょっと迷ったが、 ツモ切り。
ツモ切り。
ここでも 打ちが本手なのだろうが、そう打つと、ますます
打ちが本手なのだろうが、そう打つと、ますます 打と、一呼吸置いたのがボケてくる。
打と、一呼吸置いたのがボケてくる。
手牌の進行と共にいずれは切り出す字牌なのだが、それでも相手の手牌の進行はできるだけ防ぎたい。この兼ね合いからの 打ちが、この場合には疑問になった。
打ちが、この場合には疑問になった。
トド松、10巡目に打 。
。
そして次巡ツモアガったのが 。
。








 (ポン)
(ポン)

 抜きドラ
抜きドラ



混一2点、 が1点、場ゾロが2点、それに抜きドラが4枚で計9点。
が1点、場ゾロが2点、それに抜きドラが4枚で計9点。
9本オールというのは金額的には大きいが点数的に大したことはない。
しかし問題はそんなことではない。
 を打たなければ、トド松の
を打たなければ、トド松の でアガっていたのだ。
でアガっていたのだ。
ただし、 でアガったからといって私の方が状態が良くなるわけではない。
でアガったからといって私の方が状態が良くなるわけではない。
トド松の方も、



 という一シャンテンだったからで、
という一シャンテンだったからで、
 引きテンパイの他に
引きテンパイの他に と
と のポンテンもあるのだから、この
のポンテンもあるのだから、この はテンパイまで持つよりしかたがない。
はテンパイまで持つよりしかたがない。
ということは、この で放銃になったとしても、微妙な序盤戦の中で、単に私のアガり番だっただけの話であり、こんなことでツキが片寄りはしない。
で放銃になったとしても、微妙な序盤戦の中で、単に私のアガり番だっただけの話であり、こんなことでツキが片寄りはしない。
ところが私の方はそれとはまったく違う。 さえ打たなかったら、間違いなく
さえ打たなかったら、間違いなく でアガっていたのだ。
でアガっていたのだ。
これは最悪の結果だった。
こんなふうにモロに表に出ることの方が、実は少なく、そうならないために微妙なかけひきが交差するのだ。
役牌をギリギリまで絞るというのもそのひとつ、楽に手牌を進行させるより、できるだけ手牌を進行させないようにした方がミスが多いに決まっている。だが、手合いが揃えばなかなかミスなんかしない。結局はその局のアガリ番の人間がキッチリアガリ切ってしまうものなのだ。
アガリを逃がし、そのために相手にアガられるのが一番ツキを落とす、そんなことは十分承知していながら、ミスを打ってしまったのだ。
ドロ沼に落ちるのも当り前だった。
開始早々の 打ち、たったこれだけのことで私のツキは目にみえて落ちた。
打ち、たったこれだけのことで私のツキは目にみえて落ちた。
なんだそれくらいのことで、と思うかもしれないが、そのほんの少しのツキの差が、実はどうにもならないくらい大きい。
ミスを打ってくれる相手なら、そのぐらいはすぐに引っくり返せるのだが、相手はミスを打たない。ミスを打ってくれないと、どうしてもその少しの差が詰まらず、相手の方が一歩だけ速い。それを繰り返すと、徐々に差が開いていき、気がついたときには、もうどうにもならないぐらい大差になってしまう。
これが恐いのである。そうなってしまえば、勢いで押せる。もう少々の手順など気にする必要もない。
たとえば、一シャンテンで
 のどちらかを切り出す場合でも、先に切り出した方にはポンが入らず、テンパイで打ち出した方にポンが入る。あるいは、先に打ち出した方にポンが入っても、その動きでテンパイを引き込み、もう一方が打てる。
のどちらかを切り出す場合でも、先に切り出した方にはポンが入らず、テンパイで打ち出した方にポンが入る。あるいは、先に打ち出した方にポンが入っても、その動きでテンパイを引き込み、もう一方が打てる。
相手にこう打たれだしたら、もうダメだ。
こちらはただ耐え忍ぶのみ。次に相手がミスをしてくれるまで待つしかないのだが、なにしろ相手には迷わないですむ手牌が入り、こちらは迷う手牌ばかり。相手が先にミスをするまで持ち堪えるなどというのは至難の技といえるのだ。
ますます、差は開く一方なのである。
悔しい限りだが、さすがにトドとドンというべきか、私の 打ちの後、まったくツケ入るスキを与えてくれなかった。
打ちの後、まったくツケ入るスキを与えてくれなかった。
分厚い封筒の中味がみるみる無くなっていく。
だが、どうにも手が出せない。
こんなときほど情けなくなることもない。
2時間経つか経たないうちに、封筒の中味はきれいに無くなっていた。
しかたがなく、後ろのポケットに手をつっ込み、ゴソゴソと札束を10コ取りだした。この大金を稼ぐのに、どれだけの苦労をしたことか。今これを出しても、あっという間に取られてしまうのはみえているのだ。
それでも席は立てない。
その10コ無くなるのに1時間もかかっただろうか。
ただ相手のミスを待つ、それだけのことにどんどん大金が無くなっていく。気が狂いそうになる。しかしそれでも耐え忍ばなければならないのだ。
こんな状態になるのだけは嫌だから、序盤戦ツキの取りっこに必死になるというのに、たった一打のために………。
また違うポケットから、すぐにドンとトドに分けられてしまう札束を10コ取り出していた。これで全財産なのだ。これが無くなれば困るのはよく分かっている。大事なタネ銭なのだ。
だが、それでも席を立てない。
一度勝負を受けたからには、こんな中途半端じゃ逃げるわけにはいかない。しかし、この10コが無くなればタネは尽き、負けが確定するのである。
もう必死だった。
いや、必死なのは最初からだが、目を見開いて、一打一打に必死になったのだ。それでも1時間半の間、相手はミスを打たなかった。
とうとう、
「パンクだ」
最後の10コが無くなった瞬間、そう敗北を宣言した。
マスターの出した封筒の20コ、私の20コ、それが全て無くなったのだ。
時間にして5時間にもならない。
このレートにしても早い決着だが、ツキが片寄ってからの時間にしてみれば、まだよく待ち堪えたほうかもしれない。
(完敗だな………)
そう自分にいい聞かせていた。
その時、
「まだヤル気はあるかい」
と、言ってきたのはマスターだった。
最初、1本というレートに躊躇していた私に、
「金子ちゃん、やんなよ」
と言ってきたのもマスター………。
一瞬の間があった。
(1度は敗北を覚悟したんだ。こんな日は退いたほうがいい)
そう思った瞬間、口から出た言葉は、
「やりますよ」
だった。
(このままで終わりたくない。もう麻雀を打てなくてもいいから、もう少し打ちたい)
そのときは本気でそう思った。
「ヨシ、それじゃオレが借りてきてやるよ」
マスターは飛び出していった。
深夜の1時である。いったいどこでどう都合をつけてきたのか、
「これで泣いても笑っても最後だよ」
と、フトコロから20コを取り出していた。
“