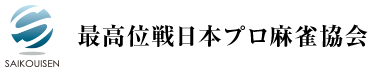パシッ。
トド松が手許に牌を引きよせた。
──ああ、アガったんだな。
そのことはすぐにわかったが、それにしても早いヤミテンだ。
まだ3巡目なのである。いったいどんな仮テン(手変りが十分考えられるテンパイ)をツモアガったのか、ヤツが手牌を開くまでのほんの短い時間、そのことには興味をそそられる。
だが、ヤツの開けた手牌はこうだった。













この手牌に をツモったのだ。
をツモったのだ。
私は心が洗われる思いがした。
トド松の2巡目 はツモ切り、つまり、この手牌のままダブルリーチをかけることができた、ということになる。
はツモ切り、つまり、この手牌のままダブルリーチをかけることができた、ということになる。
なぜ、ダブリーをかけなかったのか。その意味がわかるだろうか。
もちろん名手トド松が打っていたとなればサンマーでの話であるが、それにしても一目見て正確な答えを出せる人は、まず少ないはずだ。
順位戦の選手ならどうか。わかる人は多いと思う。いや、頭ではわかる、といった方が正解だろう。なにしろ4人麻雀なら文句なくダブリーをかける手牌なのだから(注、一〇一ではダブリーといったものはないから、どうしてもゴットウをアガりたい局面以外はやはりリーチはかけないだろうが)
それほど、このアガリは精練されている。












この手牌、ダブリーをかける必要がまったくないのだ。
ダブリーをかけなくとも
 なんていう牌が序盤早々切られることは少ない。
なんていう牌が序盤早々切られることは少ない。
つまり、手牌に役がなく、ヤミテンで出アガリできないというのは、序盤早々の内はさほど気にならない。
しかし、ツモればアガリだという点にはなんら変りはない。
そう考えればどうだろう、この手牌、大変な手変りが考えられるではないか。
まず第一に、 を引いての
を引いての












もちろん、一気通貫の2役なんかは屁みたいなもので、まるで関係ないが。







 と、
と、







この違いがわかっていても、肌でわかっている人間は意外と少ないもんだ。
それがわかっていれば、もうひとつ、まったく同じ意味合いでの変化があることにはすぐ気付く。 をポンするか、暗刻にしたとき、
をポンするか、暗刻にしたとき、









 (ポン)
(ポン)


こうなれば、

 マチでも、
マチでも、

 マチでも自在なのである。
マチでも自在なのである。
念を押すまでもないが、ダブリーの手牌が ノミになってしまうことなんかまるで関係ないのであって、あれほどアガれる手牌をアガれなくすることがツキを落とす要因、と知りながら、あの配牌をもらった時には、思わずダブリーをかけてしまうから不思議なもんだ。
ノミになってしまうことなんかまるで関係ないのであって、あれほどアガれる手牌をアガれなくすることがツキを落とす要因、と知りながら、あの配牌をもらった時には、思わずダブリーをかけてしまうから不思議なもんだ。
同じ
 をツモるにしても、その間にリーチをかけているのと、
をツモるにしても、その間にリーチをかけているのと、



 の型に直しているのとの違い。
の型に直しているのとの違い。
この違いこそ、月とスッポン、ダイヤと石コロ、いやいや、それ以上の大変な開きがある。
それほど大切な感覚なのである。
といっても、サンマーの話じゃピンとこない人もいるだろうから、同じ感覚をある局面に移行してみる。
一〇一のオーラス、現在ラスだと思っていただきたい。だが、トップまで1000点、2着、3着(同点)とは500点しか差がない(一〇一ではこういったケースが十分考えられる)
そこへ、この配牌がきたとする。












そう、さっきと同じ配牌、そして説明することも同じようなことになる。
ダブリー(ただのリーチと同じ値段だが)をかけてしまえば、トップ者はもちろん勝負には出ない。放銃すれば無条件でラスになるのだから当り前だ。流局によるトップ維持の方へ賭けることになる。
2着、3着も同じことであって、万が一ツモられても同点3着でラスはないのだから、相当な手材料が入ったとしても、相手が1巡目リーチでは守りに入る公算が大である。
つまり、リーチをかけてしまえば、
 が出る確率はほとんど無いに等しいということになる。
が出る確率はほとんど無いに等しいということになる。
では、ラス目はこの
 を自力でツモらなければならないことになるが、ツモらなければならないのなら、リーチをかけていようがいまいが条件はまったく同じ、300、600でトップになれる。
を自力でツモらなければならないことになるが、ツモらなければならないのなら、リーチをかけていようがいまいが条件はまったく同じ、300、600でトップになれる。
つまり、リーチはまったく必要ないのであって、それならば、






















 (ポン)
(ポン)


(一〇一の方が は絞られる、とそこはちょっと違うが)
は絞られる、とそこはちょっと違うが)
このふたつの変化というものが、非常に大事なものだということが見えてくる。
一〇一というのは、この点で実によくできていて、これと同じような、アガリ形に対する精練された感覚が随所に要求されるのである。
経験者でなければわからないかもしれないが、4人共が放銃しないように、相手にアガらせないようにと打つ麻雀では、アガリは気が遠くなるほど難かしい。
「ツモれば勝ちさ」というような麻雀とは一味違うのである。
その点で、麻雀の原点に近い3人麻雀と非常に類似点がある。点棒状況など関係なく純粋にアガリに向かい、アガリに対する感覚が研ぎ澄まされていくサンマーと同じように、いかにして4メンツ1雀頭を作れるか、そこに普通では考えられないほどの神経を使うことになる。
こういった、アガリに対する精練された感覚の要求された場で修行を積み重ねていって初めて、






 と
と








の違いが頭ではなく、肌でわかるようになるのだろう。
それを今、トド松がごく当り前のような顔をして、スンナリとやってのけた。
だからこそ、心の洗われる思いがしたのである。
では、この感覚が身に付くまでに、いったいどのくらいの時間がかかるものだろうか。
おそらく、何万年もの間波に洗われ続けて初めて、柔らかい部分が取れ、固い部分だけが残った海岸沿いの岩みたいなものになるのだろう。
トド松にしても、もって生まれた天分に加えて、いったいどのくらい波に打たれたことか。
だが、大部分の打ち手が、そんなめんどくさいことはやりたがらない。
もっと簡単に身に付くもので、しかも実戦に即役立つものの方へ一生懸命になり、いつしか一番大事なものを忘れてしまう。
いや、それならまだいい方で、そういった自称上級者達ばかり見た初心者は、ああ、これが上手の打ち方なのだと思い込み、最初から最も大切なことなど知らずに育つ。
かわいそうだと思うが、今のインフレルール、なまじ中途半端にそんなことを憶えるよりも、ルールに合わせた打ち方を先に憶えた方が、てっとり早く負けなくなるのだからよけい始末が悪い。
もちろん、実戦感覚といったものが必要なのは否定するつもりはない。
プロ野球の選手だって足腰を鍛えるためにランニングをする。実戦に見合った練習をしなくてはさほど上達はしないかもしれないが、基礎体力作りが一番大切なことには変りがないはず。
残念ながら、今の麻雀の世界、プロと呼ばれている打ち手でも、この最も重要な部分を大切にしている人は数少ない。
それでも通用してしまうのだ。
簡単に身に付く小手先の技と実戦感覚だけで。
その証拠に、オレは巷では勝率8割だ!とか、一晩やれば必ず一回は役満をアガる、などと豪語している打ち手が一〇一に入ってくると、それだけではどうしても勝てない。
これは当り前の話で、麻雀の最も重要な部分を鍛えるために、余計なものはできるだけ省いて作られたようなルールでは、小手先の技や実戦感覚なんかだけでは容易には勝てないのである。
それを不思議なことのように思う。
真摯な態度で麻雀に取り込んでいる若い打ち手にコロコロ負けて、
「あんなやつは賭け麻雀なら、絶対負けないんだがなー」とか、
「オレも力が落ちたもんだ」といった話になってしまう。
もっとも、忘れかけていたものを一〇一で思い出し、真摯に麻雀を打つベテラン達は、さすがに実戦経験豊富なだけに好成績をあげているが。
さて、ストーリーからはずい分と離れてしまったが、トド松の













3巡目 ツモアガリがいかにスゴいかを説明するには、最低でもこのぐらいのスペースは必要だったのである。
ツモアガリがいかにスゴいかを説明するには、最低でもこのぐらいのスペースは必要だったのである。
トド松のアガリを見せつけられて、もう勝ち負けなどどうでもよくなっていた。
麻雀の中に溶け込んでいたい、そんな澄んだ気持になっていく。
こんな気持で麻雀を打てることは滅多になく、ヤツとトコトン、技、いや麻雀を競ってみたい、そんな気持にもなっていたのである。
──数時間後。
「フゥー、今日はもうアカン」
と、常連の田上さんが手を上げた。実際、今日のトド松と私、ここに誰が入っても同じ結果になったのではないかと思うほど、2人は麻雀に没頭しきっていた。
しかしその日はもうそれで、この卓に入ってくる人間は見当たらなかった。
隣の卓ではマスターを含めて、もう丸一昼夜激闘が続いているが、そこに飛び込んでいく気もしない。だが、
──もう少し、麻雀に浸っていたい。
そんな気持は強い。
おそらくトド松の方も同じ気持だったにちがいない。手持ちぶさたに牌をもて遊んでいる姿がそう語っている。そうじゃなかったら、もうサッサと引き上げているはずだ。
そんなトド松の姿を見ているうちに、フッと、
「たまにはジックリと麻雀を打とうや」
夕方偶然出会った時に、ドンさんがそう言い残したのを思い出していた。
「まだ11時か、あの時間からなら、まだいるな」
そう思うと同時にもう指はダイヤルを回し始めていた。
「そうですか、じゃ、これから行きます」
と、オレ。
トド松が「お前も好きだな」といった感じで、こちらを見てニヤニヤしている。
「4人打ちか──」
どうも4人麻雀はなー、というその口調もどうやらまんざらでもないらしい。
「しかし、4人打ちならもう1人必要だな。それなら、ケン坊がいい。昼ごろ帰ったはずだから、そろそろ出勤して来る頃だろう。卓が割れていたらガッカリするのは見えてるよ」
トド松がそう言い終らないうちに、もう私の指はダイヤルを回し始めている。面倒くさがり屋のはずの私が、こういうことになると勝手に身体が動いてしまう。どうも不思議なもんだ。
──40分後、
「じゃ、前と同じでいいですね」
私は指を2本立てて確認した。
差しウマである。ドンさんと打つ時には、黙っていても2枚。これが恒例になっているのだが、久し振りの対戦、一応は確認しておいた方が間違いない。
「おもしろそうだな」と、トド松。
「いきますか」
「じゃ、同じくふたつ」
ドンさんは首を軽く縦に振っただけだった。で、私が代りに説明を始めた。
「配原(配給原点)を割ると、ウマが倍になるってやつですよ」
「知ってる、ビンタっていうやつだろ、今はどこにいってもそうだからな」
「じゃ、ぼくもふたつ」
こうなれば、ケン坊も黙っているはずはない。
ドンさんは、これにも軽くうなずく。
この男、サシウマを挑まれて、イヤといったことがない。なにしろ、なんでもどんどん受けるところから付いた名前なのだ、ドンさんていうのは。
しかし、この瞬間に、この麻雀の性質が決まった。
よく考えてみれば、3人共がドンさんに対して2枚といっただけで、その3人は別にニギっているわけではないのである。
つまり、この麻雀、3人対ドンさんなのであって、仮にドンさんがラスになり、3人共が配原以上あれば、3人に4枚ずつ支払うことになり、ドンさんが3コロにすれば、その逆ということになる。
この4枚というのはトップで受け取る金額の半分に相当するのだからかなり大きい。
ドンさんにとっては不利な条件、実際そうなのだが、この男、こんな条件でいつも勝ち抜く。勝てばもちろんカッパギ(スクープのこと)だ。
常連のほとんどが、なんとかやっつけてやろうと思うのだが、いつのまにかドンさんのペースになってしまう。それほど、この男の力は強大である。
だが、今日はメンバーが違う。この3人がスクラムを組めば、いかなドンとて…。
そんなことは、もちろん百も承知しているだろうが、それでも平然といつもと同じように受けるあたりがいかにもドンさんらしい。
起家はトド松に決まり、私、ドンさん、ケン坊の座順。
トド松がサイコロを振り、山に手をかけた瞬間、
「ちょっと待った、3人から外ウマ2枚ずつ!」
常連のIから声がかかった。
いつもやられているドンさんにひと泡ふかせてやろうとの魂胆だろうが、外ウマの6枚は、ちょっと大きい。だがドンさんは、これにも同じように軽くうなずいた。
“